メディア MEDIA
内部統制監査報告書とは│報告書の内容や内部統制報告制度の注意事項を解説
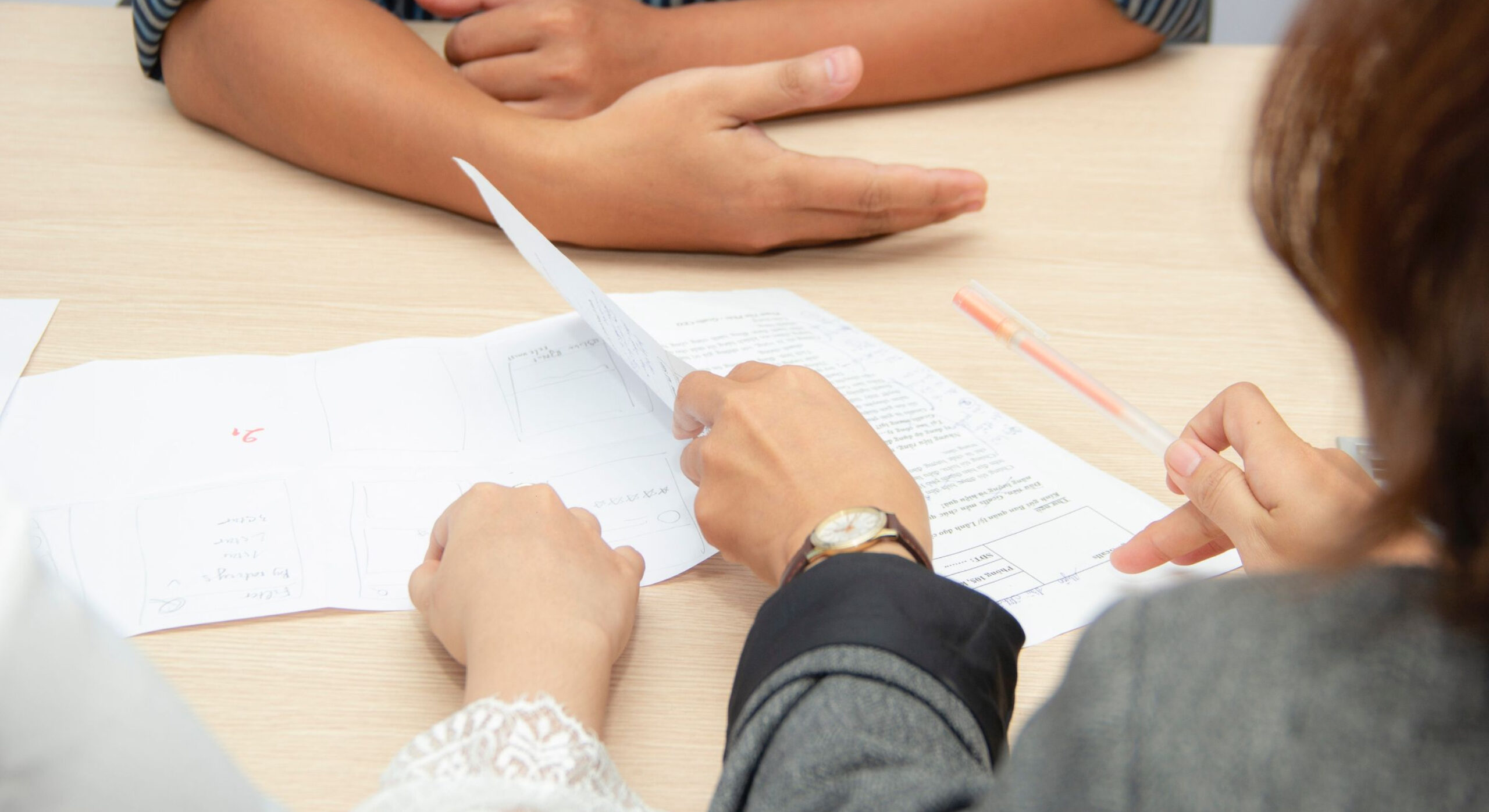
内部統制監査報告書とは、会社が作成した内部統制報告書に対する監査報告書です。具体的には、会社が実施した内部統制に関する評価方法や評価結果が適切かどうかについて、外部の監査人が独立第三者の立場からその適切性を保証するものになります。
この記事では、少し複雑な内部統制監査報告書について、内部統制監査の位置づけ、どのように実施されるのか、その注意点は何か、などを踏まえて解説します。


内部統制監査報告書とは

内部統制監査報告書とは、会社が作成した内部統制報告書に対する監査報告書です。
内部統制報告書は、内部統制報告制度(以下、J-SOX)に基づいて、自社の内部統制の有効性を評価した報告書になります。この内部統制報告書に対して、外部の監査人がその適切性を保証するために実施した内部統制監査の結果をまとめたものが内部統制監査報告書です。
ここでは、内部統制監査がそもそも何か、そして、同じような概念である内部監査や財務諸表監査との関係を見ていきましょう。
内部統制監査とは
内部統制監査とは、外部の監査人が独立の立場から、会社が実施した内部統制の評価(以下、内部統制評価)に対して、後追いで監査を実施することです。
内部統制評価と内部統制監査は同じような言葉ですが、明確に定義が異なります。
内部統制評価は、会社自らが、直接的に内部統制の有効性を検証し、報告するものです。
一方、内部統制監査は、外部の監査人が、内部統制評価の適切性を評価することで、間接的に内部統制の有効性を保証して報告するものになります。
会社が自社の内部統制の有効性を検証し、そのお墨付きを監査人が与える、という関係になっています。
金融商品取引法上、上場会社は、これらの内部統制評価や内部統制監査といったJ-SOX対応を実施しなければいけません。上場会社にJ-SOX対応が求められる理由は、一言でいえば、財務報告の信頼性を向上させ投資家を保護するためです。
なお、新規上場会社は、上場後の3年間は内部統制監査の免除を選択できます(ただし、資本金100億円以上または負債総額1,000億円以上の会社を除く)。また、内部統制監査は免除できても、内部統制報告書の提出、つまり内部統制評価は免除されませんのでご注意ください。
内部監査との関係
内部統制監査と似た言葉で内部監査があります。
内部監査は、会社の内部監査担当者が、自社の業務の進め方や判断に関して、点検チェックを実施するものです。
この内部監査には、先に述べた内部統制評価も含まれる広い概念です。
したがって、内部監査の一部である内部統制評価に対して、監査人が後追いで内部統制監査を実施する、といった関係になります。
内部監査については、以下の記事を参考にしてください。
内部統制と内部監査の違いは?両者の実施目的や内容・流れを解説
財務諸表監査との関係
財務諸表監査は、会社が作成した財務諸表に対して、重要な虚偽表示がないかどうかについて意見として表明することです。
財務諸表監査も内部統制監査も、外部の第三者である監査人が実施する点においては同じになります。
しかし、内部統制監査は、会社が作成した内部統制報告書に対する意見でしたが、財務諸表監査は、会社が作成した財務諸表に対する意見です。
つまり、監査の対象が異なります。
ただし、内部統制報告書は、財務報告に係る内部統制の有効性を評価したものであり、当然財務報告に係る内部統制が有効であれば、それによって作られた財務諸表も信頼できるものになります。
逆にいえば、財務報告に係る内部統制が有効でない場合、それによって作られた財務諸表は信頼できるか怪しいもの、ということです。
そこで、内部統制監査も財務諸表監査も、原則的には同一の監査人が実施し、内部統制監査の過程で得られた監査証拠は、財務諸表監査の監査証拠としても使うことで(逆もあり得ます)、効果的かつ効率的な監査が実施される、という関係になります。
内部統制監査の位置づけ
上記の内部統制評価含む内部監査と、財務諸表監査と、内部統制監査の違いを表でまとめると以下です。
| 内部監査 | 財務諸表監査 | 内部統制監査 | |
| 実施者 | 内部監査担当者 | 外部監査人 | 外部監査人 |
| 監査対象 | 内部統制や業務の進め方など | 財務諸表 | 内部統制報告書 |
| 報告形式 | 内部統制報告書や内部監査報告 | 独立監査人の監査報告書 | 内部統制監査報告書 |
| 判断基準 | 社内のルール | 会計基準 | 内部統制基準 |
※内部統制基準とは、財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
※内部統制実施基準とは、財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準
以上のように、主に実施者や監査対象が異なるものと理解していただくとわかりやすいかもしれません。
【文例】内部統制監査報告書の記載事項
では、内部統制監査報告書はどのようなものでしょうか。
内部統制監査報告書は、財務諸表の監査報告書と同じく、記載事項が決まっている定型的なものになります。
具体的には、以下の見出しの通りです。それぞれ記載される内容を説明します。
監査意見
ここでは、内部統制報告書に対して監査を実施した結果に対する結論が記載されます。
監査した結果、全ての重要な点において適性に記載されていると判断されれば、以下のように記載されます。
「当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、○○株式会社の×年×月×日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、○○株式会社が×年×月×日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。」
監査意見の根拠
監査意見の根拠においては、文字通り、独立第三者の立場から意見を表明するに至った根拠が記載されます。
「当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。」
内部統制報告書に対する経営者及び監査役等の責任
ここでは、会社側の責任や内部統制の限界について、以下のように記載します。
「経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。」
内部統制監査における監査人の責任
そして、実際に監査人がどのように監査を実施したか、どのような責任を果たしたかをここの段落で記載します。
「監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
- 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
- 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
- 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。」
利害関係
最後に、監査人が独立第三者として、利害関係がない旨を記載します。
「会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。」
上記のように、内部統制監査報告書は定型化されたもので、基本的にどの会社も同じ記載になります。
しかし、会社が実施した内部統制評価が不適切だった場合や、重要な監査手続が実施できなかった場合は、上記の監査意見と同じ無限定適正意見が表明されるとは限りません。
内部統制評価の不適切度合や実施できなかった監査手続の影響度合によって、限定付適正意見、不適正意見、意見不表明が記載されることもあります。
また、追財務諸表の利用者(投資家)に対して、特に強調したい点や説明することが適切と判断した点がある場合は、追記情報を内部統制監査報告書と区分した上で記載することもあります。
無限定適正意見以外の意見や追記情報は極めて稀な場合ですが、そのような意見などが存在することは覚えておいた方がよいです。
内部統制報告書と内部統制監査報告書との違い
内部統制監査報告書は上記のように、会社が作成した内部統制報告書に対して、外部の監査人が意見を述べるものでした。
しかし、内部統制報告書自体は実際に内部統制の有効性について報告するものなので、内部統制監査報告書とは異なる記載になります。
まず、内部統制報告書には表紙と本文があり、表紙には提出書類、根拠条文、提出先、提出日、会社名などが記載されます。
本文には見出しがあり、各見出しは下記の5つです。
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
3【評価結果に関する事項】
4【付記事項】
5【特記事項】
本文自体は、何に基づいて評価したか、どう評価したか、期末日時点で内部統制は有効か、などを記載します。
このように、内部統制報告書と内部統制監査報告書には、それぞれの監査対象や実施者が異なることから、報告書自体も違うものになります。
内部統制監査の実施方法

内部統制監査の概要がご理解いただけたところで、実施方法について説明します。
外部の監査人がどのように内部統制監査を進めるかを理解することで、内部統制監査を初めて受ける場合でも、スムーズな対応が可能となるでしょう。
基本的な考え方
内部統制監査は、上述の通り、内部統制評価に対する監査です。
従って、基本的には、内部統制評価を実施した後に、監査が行われます。
具体的には、内部統制評価は大きく分けると、評価範囲の決定、整備状況の評価、運用状況の評価、ロールフォワード手続、不備のとりまとめと報告、というステップに分かれます。
これらの各ステップの後に、内部統制監査として、評価範囲は問題ないか、整備・運用状況の評価手法は問題ないか、などが実施・検討される流れです。
これらのステップごとに監査が実施されない場合、のちに大きな手戻りが発生します。
例えば、運用状況の評価の段階で、評価範囲を監査した結果、評価範囲が誤ってた、ということになれば、新しい評価範囲で整備状況の評価からやり直しすることになるでしょう。
実際には、各監査法人によって内部統制監査の進め方は異なりますが、上記のやり直しを防ぐためにも各ステップが完了次第、監査を受けることが無難です。
具体的な年間スケジュール
では、具体的な年間スケジュールはどのようになっているのでしょうか。
以下は3月決算の会社における内部統制評価と内部統制監査のスケジュールの例です。
| 内部統制評価 | 内部統制監査 | |
| 評価範囲の決定 | 6月~7月 | 6月~7月 |
| 整備状況の評価 | 7~8月 | 8月~9月 |
| 運用状況の評価 | 1~2月 | 2月~3月 |
| ロールフォワード | 4月 | 4月 |
| 不備のとりまとめと報告 | 4月~5月 | 4月~6月 |
評価範囲の決定は、重要ではあるものの、前期から大きな変更がないケースが多く、内部統制評価も内部統制監査もお互いすり合わせながら合意するため、第一四半期が始まる前後の6~7月で決定されます。
整備状況の評価は、4~6月度をサンプルに、7~8月で内部統制評価が実施され、第一四半期のレビューが終わった8月以降で内部統制監査が実施されることが多いです。
運用状況の評価は、7~12月度をサンプルに、1~2月で内部統制評価が実施され、2~3月で内部統制監査が実施されます。
ロールフォワードは、統制の変更がない場合、4月に変更がない旨の回答を得て、どちらも完了です。
不備のとりまとめと報告は、不備がどの程度発生しているかにもよりますが、内部統制監査は長引いて6月に着地することもあり得ます。
上記がおおまかな内部統制評価と内部統制監査のスケジュールです。
ロールフォワードについては、次の記事を参考にしてください。
内部統制評価におけるロールフォワード手続とは?手続や確認項目を解説
内部統制監査を受けるにあたっての注意事項

内部統制監査を受けるにあたっての注意事項をお伝えします。
内部統制評価の評価書には実施した評価手続を具体的に記載する
内部統制評価は、どのような手続を実施し、どのような結果を得たか、を評価書として記録する必要があります。
また、手続と結果だけでなく、実施者、実施日、といった情報も残すべきです。
これらの情報は、内部統制監査として、外部の監査人がチェックする際に必要になります。
よって、監査人が内部統制評価の評価書を読んで理解できる程度に詳細に記載しなければなりません。
読んで理解できない場合、監査人から質問されることでコミュニケーションコストが発生したり、適切に内部監査が実施されていないのではないかという疑念を持たれたりしてしまいます。
監査人とのコミュニケーションをスムーズに行うためにも、内部統制評価の評価書には、実施した評価手続を具体的に記載しておきましょう。
不備が発生した場合、早めに監査人に相談する
内部統制評価によって、不備または不備の可能性があるものが検出された場合、早めに監査人に相談した方がよいです。
理由は、期中で不備が発生した場合、改善を実施し、改善後に再度運用状況の評価等を実施しなければならず、時間的余裕がないからです。
不備かどうかの判定は、不備が発生した理由や状況、監査人の解釈や判断によるところもあり、誤っていたという事実だけをもって行われることはありません。
ただ、不備だった場合には、追加作業が発生するので、その工数の余裕も見ながら、監査人には早めに相談しておいた方が無難でしょう。
内部統制の不備については、次の記事を参考にしてください。
内部統制の不備の事例とは?開示すべき重要な不備の判断基準も解説
場合によっては財務諸表監査の負担が増大するリスクもある
内部統制評価が適切に行われていない場合、監査人は財務諸表監査のサンプル数を増やす可能性があります。
監査人は、内部統制監査と財務諸表監査を一体的に実施するため、内部統制監査で得た監査証拠を財務諸表監査で利用します。
このように監査証拠を融通することで効果的かつ効率的な監査が実施されるのです。
しかし、内部統制監査の結果、内部統制評価が適切に行われておらず、財務諸表監査の監査証拠として使えないと判断された場合、財務諸表監査の監査証拠を追加で入手する必要が発生します。
追加で監査証拠を得るために、サンプル数を増やし、その分経理へのエビデンス提出依頼が増え、財務諸表監査の負担が増大するのです。
財務諸表監査を効果的かつ効率的に実施するためにも、内部統制監査をミスなく実施することが大切です。
まとめ

内部統制監査報告書は、会社が作成した内部統制報告書に対する監査報告書です。
内部統制監査は、会社の内部統制評価を後追いで実施されるもので、独立第三者の監査人が実施します。
内部統制監査と内部統制評価は言葉として似ていますが、意味や定義は異なります。
J-SOXの趣旨や財務諸表監査との関係性を踏まえた上で、内部統制監査を理解すれば、より効果的な内部統制評価が実施できるはずです。
Co-WARCについて
Co-WARCでは、内部統制構築、J-SOXの立ち上げ支援を含め、コーポレート課題全般の支援を行っています。
何からすれば良いかわからないから相談したい、具体的な支援内容を知りたいなど、どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
コーポレート課題を解決するプロが最適な解決策をご提案します。



関連記事
-
 2024.10.23内部統制と業務マニュアルの関係とは?作成のポイントも解説
2024.10.23内部統制と業務マニュアルの関係とは?作成のポイントも解説 -
 2024.10.10IPO準備に必要なこととは?スケジュールや期間別にやることを紹介
2024.10.10IPO準備に必要なこととは?スケジュールや期間別にやることを紹介 -
 2024.10.08PLCとは|業務プロセスに係る内部統制の概要と評価の手順を解説
2024.10.08PLCとは|業務プロセスに係る内部統制の概要と評価の手順を解説 -
 2024.10.02IPOを目指す企業が準備すべき内部統制関連の業務について解説!
2024.10.02IPOを目指す企業が準備すべき内部統制関連の業務について解説! -
 2024.09.25内部統制整備のポイントやメリットは?整備状況の評価についても解説
2024.09.25内部統制整備のポイントやメリットは?整備状況の評価についても解説 -
 2024.09.18内部統制の文書化はどうやるべき?3点セットが重要である理由を解説!
2024.09.18内部統制の文書化はどうやるべき?3点セットが重要である理由を解説! -
 2024.09.18金融商品取引法における内部統制報告制度とは?会社法との違いから提出期限・記載事項まで解説!
2024.09.18金融商品取引法における内部統制報告制度とは?会社法との違いから提出期限・記載事項まで解説! -
 2024.08.09内部統制評価で必要なサンプル数はどれくらい?一覧表を使って解説!
2024.08.09内部統制評価で必要なサンプル数はどれくらい?一覧表を使って解説! -
とは?評価方法・CLC・PLCとの違いを解説-scaled.jpg) 2024.07.22全社的な内部統制(ELC)とは?評価方法・CLC/PLCとの違いを解説
2024.07.22全社的な内部統制(ELC)とは?評価方法・CLC/PLCとの違いを解説




