メディア MEDIA
内部監査の兼務は可能?担当者選定から部門立ち上げ・外部活用まで徹底解説

内部監査は企業統治・リスク管理に不可欠ですが、人員確保が難しい場合、兼務も一般的です。しかし兼務には部門選定、独立性確保、業務負担増などの課題があり、外部リソース活用も検討事項です。本記事では、内部監査の兼務担当者選定、必要なスキル、注意点、部門立ち上げ手順、外部活用法(アウトソーシング、コソーシング)を解説し、最適な内部監査体制構築を支援します。


内部監査の役割と責任
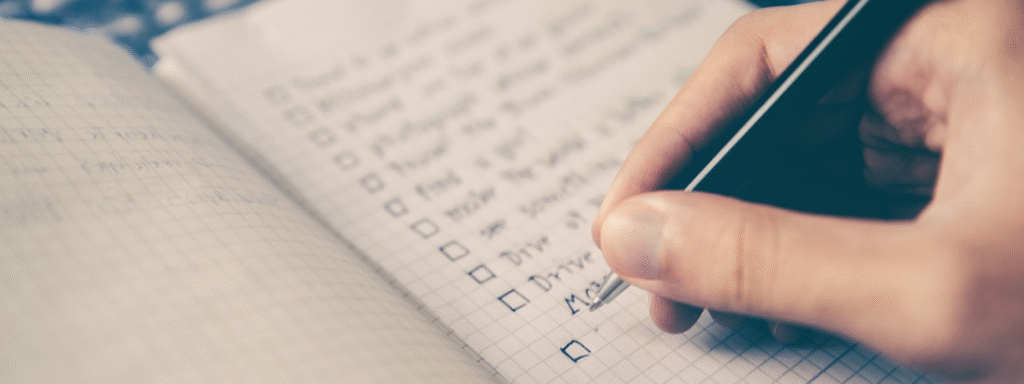
内部監査は、企業のガバナンス、リスク管理、および内部統制の有効性を評価・改善することを目的とした活動です。経営層や取締役会に対し、組織全体の業務運営が適正で効率的であるかを確認し、必要に応じて改善提案を行います。
内部監査の目的と機能
内部監査は、企業が目標達成に向けた経営資源を適切に活用しているかを評価し、業務の有効性・効率性を確保することです。また、法令や社内規程の遵守状況を監視し、リスクを最小化するための助言を行います。
具体的には、以下の3つの観点からその機能を果たします。
企業のリスク管理とガバナンスの向上
企業活動にはさまざまなリスクが存在し、これを適切に管理することが経営の安定に直結します。内部監査は、組織内でリスク管理プロセスが適切に運用されているかを評価し、リスクの特定・評価・対応状況を確認します。
また取締役会や経営層が適切な意思決定を行えるように情報提供を行い、不正行為や経営判断ミスの未然防止に寄与します。
内部統制の評価
内部統制は、業務の有効性、財務報告の信頼性、法令遵守を確保するための重要な仕組みです。内部監査では、企業が定めた業務手順や規程が実際に遵守されているかを確認し、統制が有効に機能しているかを評価します。
特に内部統制制度(J-SOX)の適用対象となる企業は、財務報告に関連する内部統制の整備・運用状況が重要視されるため、監査の結果をもとに改善提案を行うことが求められます。
不正・コンプライアンスリスクの監視
企業における不正行為や法令違反は、信用低下や財務的損失につながる重大なリスクです。内部監査は、不正リスク評価や内部通報制度の運用状況を確認し、リスクの早期発見・未然防止に努めます。また、関連法規や社内規則が遵守されているかを監視し、問題が見つかった場合には是正を促します。これにより、企業全体で法令遵守に関する意識の高まりが期待されます。
監査役・会計監査人との違い
内部監査の他に監査役や会計監査人が存在しますが、それぞれの役割や目的は異なります。これらの違いを理解することで、内部監査の位置づけや相互連携の重要性が明確になります。
以下では、監査役と会計監査人それぞれとの違いについて説明します。
監査役との違い
監査役は、会社法に基づき取締役の職務執行を監督します。主に経営者の行動や取締役会の運営が適法かつ適正であるかを監視し、株主の利益保護を重視します。
内部監査が業務全般の有効性やリスク管理の評価を主眼に置くのに対し、監査役は経営判断の適正性や不正防止に焦点を当てています。
また、内部監査は経営層に助言を行う立場であるのに対し、監査役は経営層を監督する立場です。
会計監査人との違い
会計監査人は主に財務諸表の適正性を確認するために、会計監査を行う第三者の専門家です。金融商品取引法や会社法に基づき、上場企業や一定規模以上の会社において、財務報告が正確で信頼できるものであるかを評価します。
内部監査は業務全般にわたる広範な監査を行うのに対し、会計監査人は財務報告に関連した項目に関して監査を行う点が大きな違いです。
ただし、内部監査が財務関連業務を監査する場合は、会計監査人と連携し、重複を避けつつ効率的な監査を実施することが重要です。
内部監査部門の立ち上げ

内部監査部門の立ち上げは、特に上場準備段階や企業規模拡大の過程で、リスクマネジメント強化やガバナンス向上のために重要です。
以下では、立ち上げの流れ、内部監査部門の位置付け、および規模に関するポイントを解説します。
立ち上げの流れ
内部監査部門の立ち上げは、以下の段階を踏んで進めます。
- 現状分析と課題の把握: 企業の現状を評価し、内部監査で対応すべきリスクや問題点を特定する。
- 内部監査規程の制定: 監査の目的、対象範囲、実施方法を定めた規程を作成する。
- 内部監査責任者とメンバーの選定: 内部監査室長を含めた担当者を選任し、役割分担を明確にする。
- 年間監査計画の作成: 優先度やリスクレベルに基づき、年間の監査スケジュールを策定する。
- 監査手続の整備: 実施時に使用するチェックリストや手続書を作成し、品質の一貫性を確保する。
- 実施・評価・改善: 実際の監査を実施し、結果を報告した上で改善提案を行う。
立ち上げ段階では、初期の負担を軽減するためにアウトソーシングやコソーシングも有効です。
内部監査部門の位置付け
内部監査部門は、組織上、最高経営責任者(CEO)や取締役会に直属する形が望ましいとされています。これは、監査対象となる部門からの独立性を確保し、経営層への迅速かつ正確な報告を実現するためです。監査役会や会計監査人との連携も重要であり、三様監査(内部監査・監査役監査・会計監査)の効果的な実施が求められます。
内部監査部門の規模
内部監査部門の規模は、企業の規模や業種、リスクの多様性により異なります。一般的に、以下の要素を考慮します。
- 企業規模: 大企業では専任の内部監査人を複数配置しますが、中小企業では兼務体制を取ることもある。
- 事業の複雑さ: 事業が複雑であるほどビジネスリスクが多数識別されるため、内部監査で対応すべき項目が増える。
- 海外拠点や子会社の数: 海外拠点や複数の子会社を持つ企業は、広範囲にわたる監査が必要なため人員を厚くする傾向がある。
- リソース確保: 専任者の確保が困難な場合は、外部専門家を活用したコソーシング体制が有効である。
最適な規模の内部監査部門を構築することで、業務の有効性評価やリスク対応が円滑に進み、企業の健全な運営に寄与します。
内部監査担当者の選定基準
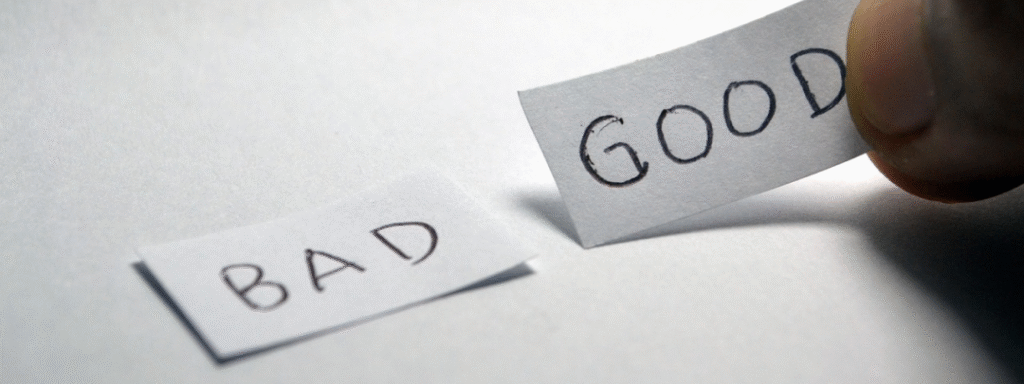
内部監査の有効性を高めるためには、適切なスキルと経験を持つ担当者を選定することが重要です。以下では、内部監査担当者に求められるスキルや経験について、具体的な基準を解説します。
内部監査担当者に求められるスキルと経験
内部監査担当者は、業務の正確な評価や改善提案を行うため、会計・財務知識やリスク管理のスキル、さらには高いコミュニケーション能力が求められます。以下の項目は、内部監査担当者として重視されるスキルの代表例です。
会計・財務の基礎知識
内部監査では、財務報告の適正性やコスト管理状況を評価する機会が多く、貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)の読み解きができることは、財務リスクの特定や不正防止に直結します。J-SOX対応企業は、財務報告に関する内部統制の評価が求められるため、特に重要です。
監査手法・リスク管理の知識
リスクアプローチに基づいた監査計画を立て、優先度に応じた監査を実施するために必要です。リスクマネジメントの考え方を理解することで、業務の改善提案や不正リスクの低減につながります。特に、外部監査人や監査役との連携をスムーズに行う上でも、監査基準や実務経験が重要です。
コミュニケーション能力と倫理観
コミュニケーション能力は被監査部門との調整や経営層への報告など、あらゆる場面で必要です。担当者は、問題点を明確かつ適切に伝える力を持つことが求められます。問題点を明確かつ適切に伝える力、高い倫理観、公正さ、情報の機密性を守る姿勢が求められます。内部監査は、情報の機密性を守りつつ、企業全体の信頼性向上に寄与する役割を担っています。
社内のどの部門から選出すべきか?
内部監査担当者の選定は、企業のニーズやリスクに応じた選定が必要です。以下では、選出元として考えられる代表的な部門とその特徴を紹介します。
コーポレート部門
企業のコーポレート部門から内部監査担当者を選定する場合があります。
経理・財務部門
経理・財務部門出身の担当者は、会計処理や財務報告に関する知識が豊富であり、財務リスクの特定やJ-SOX対応の評価に強みを持ちます。ただし、経理業務と内部監査を兼務する場合、監査時には独立性が損なわれないように配慮が必要です。
その他(総務・法務・人事労務)
総務や法務、人事労務から選出された担当者は、会社全体のルールや規程に精通しており、コンプライアンス監査や契約関連のリスク評価に強みを持ちます。法務出身者は、規程の整備やリスク対応に関する助言を行いやすく、内部監査の実務にも適しています。
ただし、コーポレート部門が内部監査担当者を兼務する場合は、自己監査とならないように注意が必要です。例えば、総務部から内部監査担当者を選定する場合、その担当者は総務部の業務に対する監査を担当できません。その場合は、他部門から選定した担当者が対応したり、外部の人材が対応したりします。
事業部門のマネージャー
事業部門から選出されたマネージャーは、業務を理解しているため、業務改善に向けた具体的な提案が可能です。特に、生産や営業部門から選出された場合、現場視点での課題発見がしやすくなります。ただし、自部門の監査は自己監査を避けるため、クロス監査の実施や他部門との連携が求められます。
IT部門(システム監査が必要な場合)
IT担当者は、システムの運用状況や情報セキュリティに関する知識を有しており、情報漏洩リスクやIT統制の評価に強みを持ちます。特に、近年ではリモートワークの普及やクラウドシステムの活用が進む中で、IT関連リスクの重要性が増しています。IT部門から選出する際は、技術面に偏りすぎず、経営視点を持つ人材を選ぶことが望ましいです。
内部監査の進め方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
内部監査とは?進め方やチェックリスト項目、被監査部門の準備事項を解説
内部監査の兼務は可能か?

内部監査を専任で担当することが望ましいものの、特に中小企業や上場準備段階にある企業では、リソースやコストの制約から専任者を配置することが難しい場合があります。このような場合、他の部門の担当者が内部監査を兼務することができます。
内部監査の兼務には独立性や業務負担といった課題が伴うため、適切な対応が求められます。内部監査の兼務は、企業の直面する課題に対する現実的な事情を踏まえた選択肢の一つです。しかし、内部監査の兼務は、独立性の確保や業務過多への配慮がなされない場合、監査の実効性が損なわれるリスクがあります。したがって、内部監査の兼務を検討する際は、業務分担の明確化や外部リソースの併用を含めた体制整備が重要です。
兼務する際のポイント
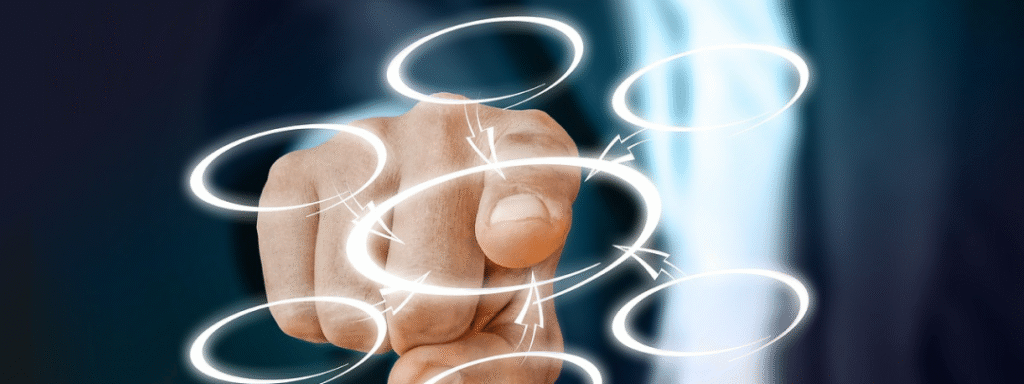
内部監査を兼務で実施する場合、独立性の確保や業務負担のバランスに十分配慮する必要があります。業務過多や高度な専門性が求められる場合、兼務体制では十分な監査が困難なことがあります。こうした状況では、内部監査を外部にアウトソースすることが有効な選択肢となります。
内部監査を外部にアウトソースする
内部リソースが不足している場合や、専門性を迅速に取り入れたい場合に有効な手段です。ここでは、アウトソーシングのメリットとデメリットについて詳しく解説します。
アウトソーシングのメリット
アウトソーシングを活用し得られる主なメリットは次の通りです。
- 専門性の確保
最新の監査手法や業界知識を有しており、高品質な監査が可能。また、内部監査に関する専門家の手法や知見を理解し、自社の内部監査部門のナレッジとして蓄積することができる。 - 独立性の確保
社内での兼務によって発生しやすい独立性の問題を回避できる。部の第三者として客観的かつ公正な立場から監査を実施するため、経営層や取締役会への報告においても信頼性が高まる。 - リソース確保
専任者の採用・育成より短期間で監査体制を構築でき、リソース不足にも柔軟に対応できる。また、必要な期間のみ契約できるため、コストの最適化にもつながる。
アウトソーシングのデメリット
一方で、アウトソーシングには以下のようなデメリットが存在します。
- 社内の知識が蓄積されない
外部委託に依存しすぎると、内部監査に関するノウハウが社内に蓄積されず、長期的には自立した監査体制の構築が困難になる。将来的に内部監査部門の内製化を目指す場合、社内人材の育成を並行して進めることが必要。 - 自社の業務理解に時間がかかる
外部の専門家が自社の業務フローや文化を十分に理解するまでには一定の時間がかかる。この理解が不十分なまま監査を実施すると、表面的な指摘にとどまり、実務に即した改善提案が得られないこともある。
内部監査のコソーシング(社内外の併用)
内部監査のコソーシングとは、社内の監査担当者と外部の専門家が共同で監査業務を実施する手法です。外部依存を抑えつつ、専門性の確保や社内リソースの有効活用が可能になります。
コソーシングの活用例
コソーシングは、企業のニーズや体制に柔軟に対応できます。以下は、一般的な活用例です。
- 上場準備段階での活用
IPO準備中の企業では、監査計画の策定から実施、報告までを社内担当者と外部専門家が共同で進めスムーズな審査対応が可能。 - 特定分野の専門支援
ITシステム監査や海外子会社監査など、社内に専門知識がない分野で外部の専門家を活用。 - 定期的な監査の補助
繁忙期のみ外部専門家を追加し、社内リソースの不足を補う。
コソーシングのメリット
コソーシングには、アウトソーシングにはない以下のようなメリットがあります。
- 社内リソースの有効活用
社内担当者が既存の業務知識を生かした効果的な監査が可能。 - 専門性の補完
高度な監査技術や業界特有の知識を取り入れ、監査の精度が向上する。 - 監査ノウハウの蓄積
社内担当者が外部専門家と共同作業を行うことで、スキルや知識が社内に蓄積できる。
監査法人・コンサルティング会社との連携
監査法人やコンサルティング会社との連携は、内部監査の質を高め、監査対象範囲の拡大や専門的な助言を得る上で重要です。ここでは、監査法人の活用方法と、内部監査と外部監査の効果的な連携について解説します。
監査法人の活用方法
監査法人は主に会計監査を担当しますが、以下のような場面で内部監査との連携が必要です。
- J-SOX対応支援
財務報告に関する内部統制の評価や整備について、監査法人の知見を活用できる。 - リスク評価の共有
監査法人が実施する外部監査の結果を共有し、内部監査でのフォローアップや改善提案に生かす。
内部監査と外部監査の連携
三様監査(内部監査・監査役監査・会計監査)間で連携することで、監査の重複を避けつつ、相互補完的な監査体制を構築できます。以下のような連携が効果的です。
- 監査計画段階での連携
監査対象範囲やリスク評価を共有し、内部監査と外部監査が異なる視点で重要事項をカバーできる。 - 監査結果の共有と改善策の整合
内部監査の結果を外部監査人に報告し、指摘事項や改善提案に一貫性を持たせる。
まとめ
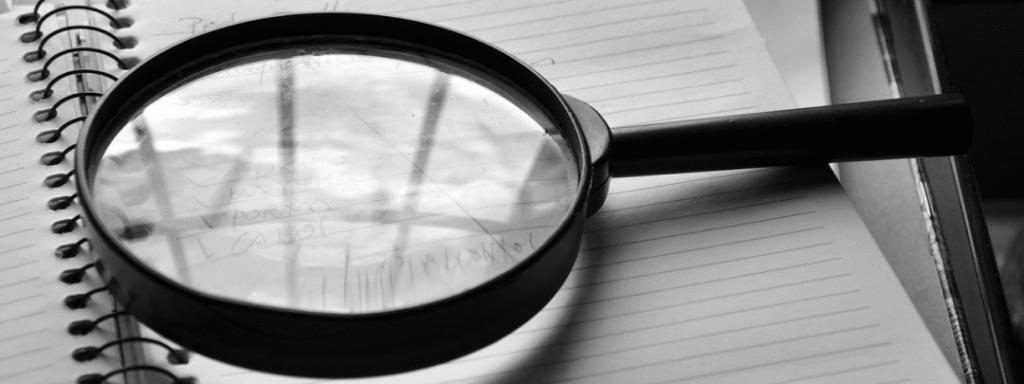
内部監査の兼務は、リソースが限られた状況下での有効な手段ですが、独立性確保と業務負担調整が課題です。担当者選定では、専門知識と自己監査防止のバランスが重要であり、役割分担の明確化と外部専門家の併用が成功の鍵となります。兼務が困難な場合はアウトソーシングやコソーシングも選択肢であり、外部リソース活用と社内ノウハウ蓄積のバランスが、長期的なガバナンス強化に繋がります。
この記事を通じて、内部監査を兼務で実施する際のポイントや外部活用の方法を具体的に理解できたのではないでしょうか。 自社の状況に合った最適な体制を構築し、持続可能な内部監査の運用に取り組みましょう。











